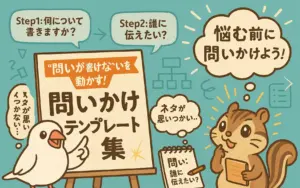集客ブログ構築サポーターの瀬戸内ことりです。
この記事をお読みいただくと得られるもの。
- 「伝わりにくい表現」がどんなものか理解できる
- 書きやすさより「読みやすさ」が優先される理由がわかる
- 実践的な言い換え例30個
- 文章改善の考え方とチェックポイントがわかる
- 読者に伝わるブログづくりの第一歩が踏み出せる
書きやすいけど伝わらない言葉の例
ブログを書いていると、「自分ではしっくりきた言葉」でも、読者に意味が伝わりにくいことがあります。
特に多いのが、「それっぽく書けてるけど、パッと意味が取れない」表現です。
例えば「〜しかねない」という言い回し。
ビジネス文書やマニュアルではよく見ますが、ブログの読者がスッと理解できるとは限りません。
この処理では誤作動を招きかねません。
改善例
この処理は誤作動が起きる可能性があります。
読みやすさとは、「書き手の思考をなるべく加工せずに、読み手が理解できるか」という視点で整えることです。
自分中心の言葉選びを見直すことで、伝わる文章に変わります。
読者に伝わる言葉選びのコツ
難解語は避ける、または言い換える
専門用語や硬い表現は、それを理解できる読者にしか届きません。
以前 SEO のご相談にいらした整体師さんは、ウェブサイトで「最新の機械で治療に当たる」ことを大きく謳っておられましたが・・・
その言葉で検索する読者はほとんどいないという事実にお気付きでなかったんですね。
そこで

これって有名な機械なんですか?
例えば「アップルウォッチ」のように、誰でも名前を知ってるものですか?
とお尋ねするとハッとされ、

言われてみれば。
この機械の名前では探さないですよね・・・。
読みやすい文章とは、「読者が検索しそうな言葉」で、「日常的な語彙」を使って構成するものです。
自明表現を削る
ブログは「自分の意見を述べる」場ですから、「個人的には」は不要です。
個人的には、こちらの方法がおすすめです。
改善例
- こちらの方法がおすすめです。
- 私はこちらの方法をおすすめしています。
無意識に入れがちな表現ですが、カットすることで文章が引き締まり、説得力が増します。
冗長表現を避ける
読み手の集中力は一文ごとに左右されます。
特に日本語では「ですけれども」「〜というふうに思います」などの回りくどい表現が文章を重たくするため、できるだけ削りましょう。
読者は○○が知りたいなというふうに思ったときに検索します。
改善例
読者は○○を知りたいときに検索します。
主語・述語の距離が遠くなると、それだけ理解に時間がかかります。
言い換えではなく “削る” という視点も大切です。
読者が理解しやすい言い換え例30選
抽象 → 具体
| 元の表現 | 言い換え例 |
|---|---|
| 支援する | 操作方法を一緒に確認する |
| 影響がある | 動作が遅くなる可能性がある |
| よくない | 読者が離脱する可能性がある |
| 問題がある | データが表示されないことがある |
| 不具合が起こる | 表示が崩れることがある |
難 → 平易
| 元の表現 | 言い換え例 |
|---|---|
| 考慮する | 考える |
| 検討する | よく見て (考えて/相談して) 選ぶ |
| 示唆する | ヒントになる |
| 考察する | 理由を考える |
曖昧 → 明確
| 元の表現 | 言い換え例 |
|---|---|
| ある程度 | 8割がた |
| 何となく | 明確な目的がないまま |
| とにかく | 理由はともかく |
| それなりに | 十分ではないが多少は |
| 多分 | おそらく |
自明表現 → 省略 or 置き換え
| 元の表現 | 言い換え例 |
|---|---|
| 個人的には〜 | (削除) |
| 私は思いますが〜 | 〜と考えます |
| 〜というふうに思います | 〜と思います |
| 〜と思っていたりします | 〜と思います |
| 〜と考えていたりもするのですが | 〜と考え (てい) ます |
言い換えに迷ったときのチェックポイント
- その言葉、読者は検索しますか?
- それ、もっと短く言えませんか?
- 自分の考えを述べる場で前置きは必要ですか?
読みやすさは「読み手のスムーズな理解」を目的にした工夫の積み重ねです。
読まれる文章は「読者目線」の積み重ね
ブログは、自分の考えを誰かに届けるための場です。
でも、「書きやすい」=「読みやすい」ではありません。
- 読者が検索しそうな言葉
- 読者が知りたい情報
- 読者が理解しやすい構造
この3つが揃って初めて、ブログは “伝わる文章” になります。
ことり式では、こうした「読者に届く文章」の組み立て方を、再現可能なかたちでお伝えしています。

「伝えたつもりなのに、反応がない」とお悩みの方は、いつでもご相談くださいね!